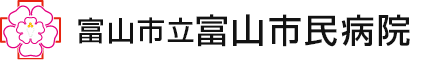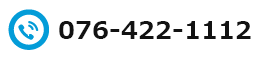医療関連感染とは?
医療関連感染とは、医療サービスを受ける過程または提供する過程で、各種微生物に暴露することにより発生する感染症です。
原因は?
医療関連感染は、人から人または医療器具などを媒介として感染し、特に、免疫力の低下している新生児、高齢者などでは通常の病原微生物だけでなく、感染力の弱い細菌による感染(日和見感染)を起こす場合があります。
院内感染対策委員会の取り組み
このような医療関連感染に対して、予防と感染症発生時に適切かつ迅速な対応を行う「院内感染対策委員会」を組織し、この下部組織として「感染対策推進委員会」を設け実働部隊の役割を持って、感染の発生予防や感染の発生時には拡大防止に努めています。
院内感染対策委員会の活動は
院内を利用する全ての人を医療関連感染から守るため、最新の知見に基づき院内のルール作りを行っています。
下部組織の感染対策推進委員会では、職員の基本的な感染対策遵守状況の把握や、感染対策の徹底などの啓発活動を行っています。