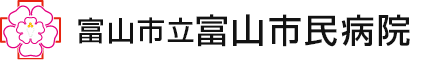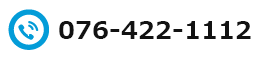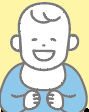
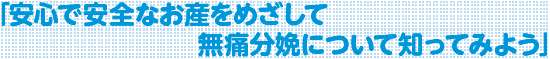 ←ここをクリックすると動画が見れます https://youtu.be/uL4pEVPlfX0
←ここをクリックすると動画が見れます https://youtu.be/uL4pEVPlfX0
当院では2010年から麻酔科医の協力を得て、硬膜外麻酔を用いて分娩時の産婦さんの痛みを緩和する無痛分娩を行っています。
出産時の痛みは、子宮の収縮そのもの(主に分娩第一期の痛み)と、赤ちゃんが狭い産道を通る際にその周りが引き延ばされることで発生するもの(主に分娩第二期の痛み)とがあると考えられています。一部の研究では、その痛みは骨折より強く、手の指を切断した痛みに匹敵するともいわれています。これを麻酔薬で生理痛かそれ以下程度まで和らげるのが無痛分娩であり、完全に痛みがなくなるわけではないため和痛分娩と称する施設もあります。
麻酔といっても眠るための麻酔ではなく、背中から痛み止めの麻酔の注射を行います(硬膜外麻酔)。脊椎の中の硬膜外腔というスペースに細い管を挿入し、そこから局所麻酔薬を注入します。当院では、薬剤の注入は機械により時間ごとに自動的に投与されますが、それに加えて産婦さんが助産師と相談しながら薬剤を追加投与することもできますので、自分のお産の進行に沿った痛みのコントロールをすることができます。硬膜外麻酔は、全身に麻酔薬を投与する方法とは異なり、狭いスペース(硬膜外腔)にいれるため薬剤は少量で済み、赤ちゃんへの麻酔薬の影響は小さく、問題にならないことがほとんどです。
硬膜外麻酔では痛みの神経は遮断しますが、下半身の運動神経を完全に遮断するわけではありません。ですから、出産の痛みはコントロールされていても(痛みの感じ方には個人差があります)、自分の力でいきむことができ、子宮が収縮してお腹の張る感覚や、赤ちゃんが生まれてくるときの感触もしっかり味わうことができます。出産時の痛みが和らぐため、痛みで取り乱すことなく落ち着いて新しい家族を迎えることができます。また、陣痛の痛みをこらえることで起こる体力の消耗を避けることができ、その分母体疲労が少なく産後の育児をスムーズに開始できることにもつながります。
過去に無痛分娩中に起きた事故の報道があり、無痛分娩に不安を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。確かに医療行為である以上、いくらかの副作用・合併症が起こる可能性はあります。しかし、当院では硬膜外麻酔の経験が豊富な麻酔科医が全例の無痛分娩を担当し、スタッフ間で定期的な勉強会も行うなど、"もしも"の時にも迅速で適切な対処ができるよう努めています。"無痛分娩"という選択肢を考慮されている方は、ぜひ一度ご来院ください。
●当院での無痛分娩について(硬膜外麻酔による無痛分娩に関する説明書.pdf)
●入院中のスケジュールについて(診療計画書)
●麻酔は当院麻酔科医師が担当しています(麻酔科医師紹介)
●麻酔科医の無痛分娩に関する経歴と研修履歴 2024年10月現在
松浦康荘
・無痛分娩麻酔管理者
・麻酔科専門医、標榜医
・無痛分娩経験年数 13年(2012年から)
・安全な産科麻酔の実施と安全管理に関する最新の知識の習得及び技術の向上のための講習会(JALAカテゴリーA講習)受講済み
本田康子
・麻酔科専門医、標榜医
・無痛分娩経験年数 3年(2022年から)
津田翔
・麻酔科専門医、標榜医
・無痛分娩経験年数 7年(2016年から)
千田彬夫
・麻酔科専門医、標榜医
・無痛分娩経験年数 5年(2019年から)
又野萌
・麻酔科標榜医
・無痛分娩経験年数 1年(2024年から)
・産科麻酔に関連した病態への対応のための講習会(JALAカテゴリーB講習)受講済み
- 急変時の対応について
・母児の状況により緊急帝王切開や児の管理が必要と考えられる場合には、麻酔科や小児科と速やかに連携して対応しています。
・母体に集中治療が必要とする場合はICUで治療を行います。
・必要に応じて富山大学附属病院や富山県立中央病院へ母体搬送や新生児搬送を行っています。
・無痛分娩で用いる硬膜外麻酔に関連した合併症(高位脊椎麻酔、局所麻酔薬中毒)に対する危機対応シミュレーションを産科医、麻酔科医、助産師が参加して定期的に実施しています。硬膜外麻酔に関連して起こりうる合併症の初期症状を早めに認知し、その対応を学ぶことを目的に行っており、無痛分娩の安全な提供体制の構築に努めています。(最終の危機対応シミュレーショントレーニングはA緊急帝王切開について2025年3月14日に実施しました。参加者:産婦人科医、麻酔科医、助産師、手術室看護師)
- 日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業へ協力しています。